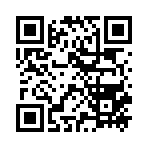2018年01月11日
奥浜名湖の「ひよんどり」と「おくない」
奥浜名湖観光協会の加治です♪
明けましておめでとうございます!!
本年も奥浜名湖ツーリズムセンターだよりをよろしくお願い致します。
さてさて、奥浜名湖のお正月といえば「ひよんどり」と「おくない」!
奥浜名湖には長い長い歴史を持つ伝統芸能がいくつも残っています。
数あるうちの3つ
「寺野のひよんどり」
「川名のひよんどり」
「滝沢のおくない」
に行ってきましたので、その様子をアップしたいと思います☆彡
まずは、寺野のひよんどりから♪
寺野のひよんどりは
毎年1月3日に行われ、無病息災や五穀豊穣、子孫繁栄を祈願する祭礼です。
国指定重要無形民俗文化財に指定されており、中世からの長い歴史があります。
会場は三遠南信自動車道 渋川寺野ICを降りてすぐの直笛山宝蔵寺です。

亀之丞(のちの井伊直親)が信州松源寺から井伊谷に戻る際に、
このお堂に寄進したといわれています。
「直笛山」(ちょくてきざん)という山号ですが、直親の「直」に寄進した「笛」にちなんでいると伝えられているのです。
そんな井伊直虎ゆかりの地で行われている祭礼なんですね!
巫女の舞、順の舞と続き、片剣の舞や両剣の舞が披露されます。
片剣の舞、両剣の舞で使われる剣は「真剣」
本物の刀なので、かなりの重さがあるそうです。

日が沈みあたりが暗くなった18時頃、クライマックスの「鬼の舞」が始まりました。
鬼が斧で火を消す様は迫力満点です!

宝蔵寺
明けましておめでとうございます!!
本年も奥浜名湖ツーリズムセンターだよりをよろしくお願い致します。
さてさて、奥浜名湖のお正月といえば「ひよんどり」と「おくない」!
奥浜名湖には長い長い歴史を持つ伝統芸能がいくつも残っています。
数あるうちの3つ
「寺野のひよんどり」
「川名のひよんどり」
「滝沢のおくない」
に行ってきましたので、その様子をアップしたいと思います☆彡
まずは、寺野のひよんどりから♪
寺野のひよんどりは
毎年1月3日に行われ、無病息災や五穀豊穣、子孫繁栄を祈願する祭礼です。
国指定重要無形民俗文化財に指定されており、中世からの長い歴史があります。
会場は三遠南信自動車道 渋川寺野ICを降りてすぐの直笛山宝蔵寺です。

亀之丞(のちの井伊直親)が信州松源寺から井伊谷に戻る際に、
このお堂に寄進したといわれています。
「直笛山」(ちょくてきざん)という山号ですが、直親の「直」に寄進した「笛」にちなんでいると伝えられているのです。
そんな井伊直虎ゆかりの地で行われている祭礼なんですね!
巫女の舞、順の舞と続き、片剣の舞や両剣の舞が披露されます。
片剣の舞、両剣の舞で使われる剣は「真剣」
本物の刀なので、かなりの重さがあるそうです。

日が沈みあたりが暗くなった18時頃、クライマックスの「鬼の舞」が始まりました。
鬼が斧で火を消す様は迫力満点です!

宝蔵寺
川名のひよんどりは毎年1月4日に万福寺薬師堂にて行われています。
こちらも五穀豊穣、子孫繁栄を祈願する祭礼で、
国指定重要無形文化財に指定されています。
ここ川名は井伊直平公ゆかりの地で、
大河ドラマでも川名の地名がたびたび登場しました。
川名のひよんどりは、
若者とタイトボシ(大松明)のもみ合いは迫力があり見どころとなっています。

滝沢のおくないは1月4日の午前中から林慶寺にて行われました。

午前中、もみ飯まつりという神事が行われ、
豊作を祈願し、滝沢の住民が東西に分かれて藤蔓を引き合います。
もみ飯まつりの後、七草がゆを作ります。
七草を刻む時に
「唐土の鳥が、日本の国へ 渡らぬ先に、七草なずなでストトントン」
と唱えます。

出来上がったの七草がゆは祭りの参加者に振舞われました。
優しくてとても美味しかったです(*^-^*)

今年取材に伺えたのは
この3つのお祭りですが、全て6つ伝統芸能が奥浜名湖に残っています。
歴史ある伝統を代々守り次いでいる地元の方々に頭が下がりますね。